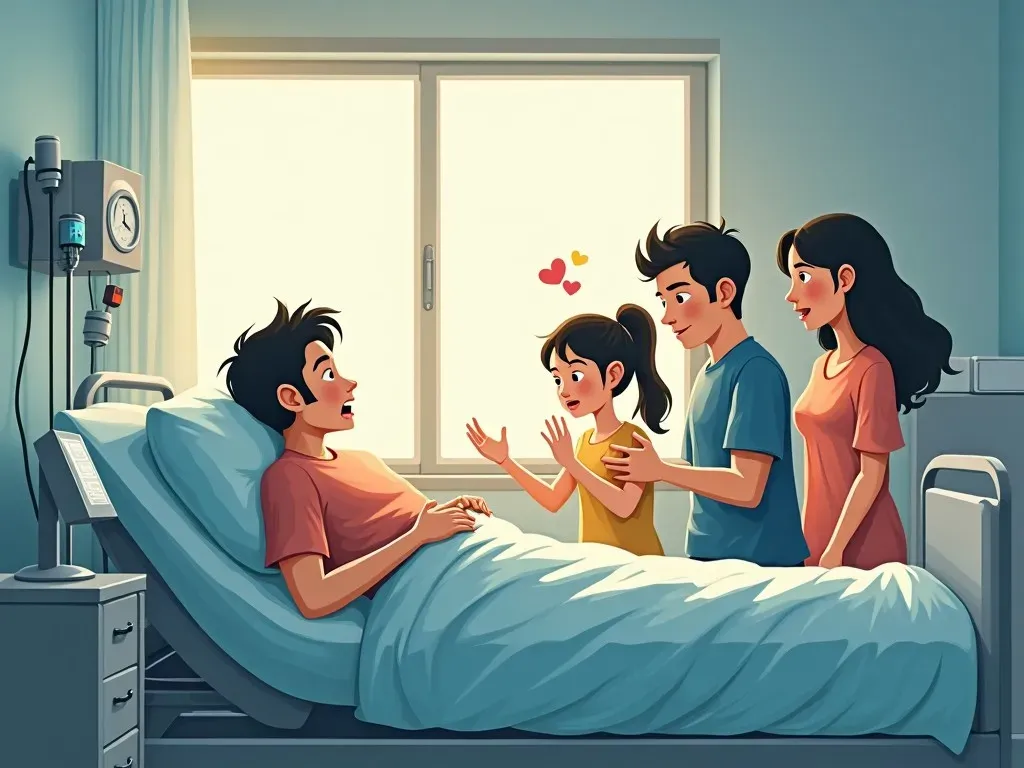危篤とは、命の危険が迫っている状態を指します。患者の容体が急変し、医師から回復の見込みがないと判断されたときに使われる用語です。家族や親しい友人がこの状態にあるとき、何をすべきか分からず、焦りや不安を感じることが多いでしょう。そんな時、冷静に行動するためには、事前に危篤について理解しておくことが非常に重要です。この記事では、危篤とは何か、その特徴や家族がとるべき行動、そして危篤状態の患者への対応方法について詳しく解説します。
危篤の状態を把握しておくことで、冷静な判断ができ、状況に応じた適切な行動が取れるようになります。また、医療機関との連絡や葬儀の準備など、さまざまな面でのスムーズな対応が期待できます。これにより、心の準備をしつつ、必要な手続きを進めることができます。
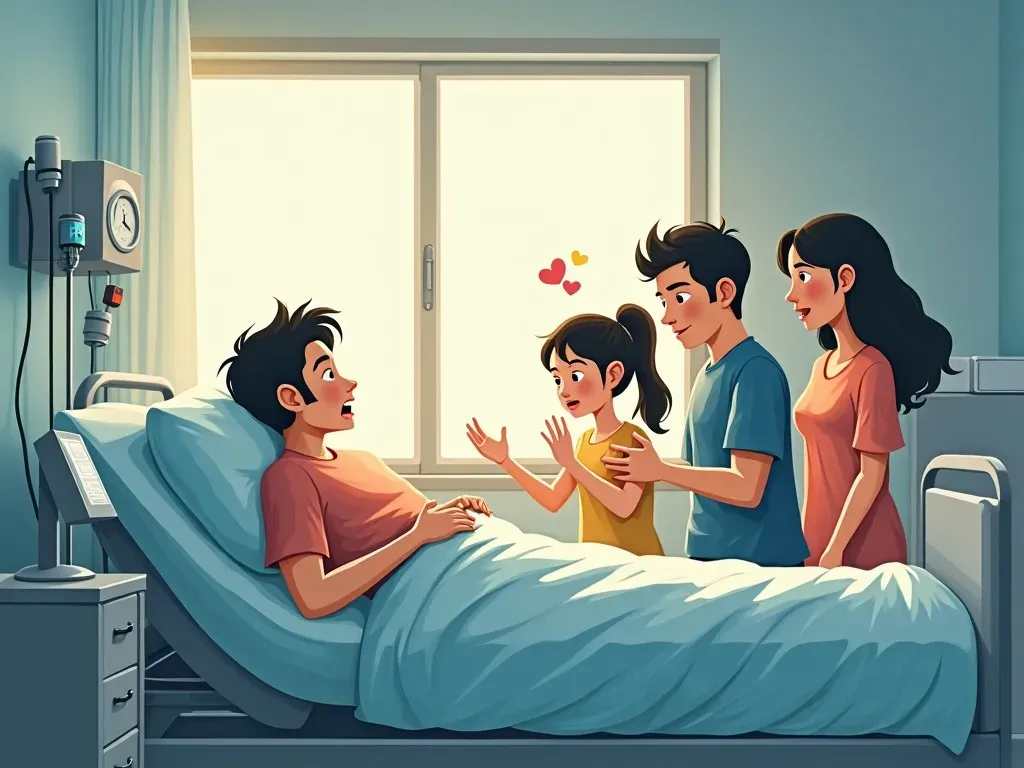
危篤の定義とその状態
危篤とは、医師が患者の容体が今にも危ないと判断した状態であり、一般的に病気や怪我の結果として現れます。危篤状態になると、回復の見込みが非常に低く、いつ命が救えなくなるか分からない状況です。この状態は、事故や重篤な病気、手術後の合併症など、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。
日本では、危篤に関する明確な定義は法律で定められていないものの、主に医療従事者がこの状態を判断する基準となっています。具体的には、以下のような症状が見られます:
- 意識がない
- 呼吸が極端に弱い
- 心拍数が急激に減少している
- 他の臓器に深刻な影響が出ている
このような状態では、医療チームが全力を尽くしても回復が難しい場合が多いため、家族や親しい友人がどのようにサポートできるかを考えておくことが大切です。
病院での危篤患者の数
日本における危篤状態の患者数は、年々増加傾向にあります。例えば、2021年の調査によれば、病院での危篤患者の割合は約8%に達しています。この数字は、高齢化社会に伴い、重篤な病気や事故が増加していることを反映しています。
| 年 | 危篤患者割合 |
|---|---|
| 2019 | 6% |
| 2020 | 7% |
| 2021 | 8% |
| 2022 | 9% |
【出典】厚生労働省
危篤と重篤の違い
危篤と重篤は、非常に似た用語ですが、実際には異なる意味を持ちます。危篤は「命の危険が迫っている状態」を指し、回復の見込みが薄い状況を意味します。一方で、重篤は「危険な状態だが、まだ回復の見込みがある」というニュアンスを含みます。
例えば、重篤な患者は集中治療室で手厚いケアを受けることが多いですが、危篤状態の患者は回復が困難とされ、場合によっては終末期のケアに移行することがあります。このため、家族がどのように対応するかが大きく変わってきます。
家族がするべきこと
危篤の連絡を受けた場合、まずは心を落ち着かせ、落ち着いて行動することが重要です。以下は具体的なステップです:
- 病院へ行く準備をする:服装や身の回りのものを整え、必要な情報(診察券、保険証など)を持っていきましょう。
- 連絡をする相手を考える:親族や友人、職場の関係者に連絡を入れる必要があります。相手に何をどのように伝えるかを考えておくと良いでしょう。
- 心の準備をする:危篤の状態は非常に厳しいものです。自分自身が心の準備をすることで、落ち着いた行動が可能になります。
さらに、病院到着後は医師や看護師からの説明をしっかりと聞き、理解することが大切です。
危篤状態への対応
危篤状態になった際の家族の対応を理解しておくことで、緊急時にはすぐに行動を起こすことができます。以下に、危篤患者を持つ家族がどのように対処すべきかについて詳しく説明します。
医療チームとのコミュニケーション
医療チームとのコミュニケーションは、危篤の状態を理解し、正しい判断を下すために重要です。医師からの説明を聞く際は、質問をすることをためらわないようにしましょう。以下のポイントを知っておくと、より効果的です:
- どのような症状が出ているのか
- どのような治療が行われているのか
- 予後についての見通し
医療従事者は患者の状態に関する情報を提供する義務がありますので、不明点は遠慮なく尋ねましょう。
情報の整理
病院に到着したら、家族や親しい友人がどれだけの情報を持っているかを整理することも重要です。必要な連絡先や患者の基本情報を揃えておくことで、急な問い合わせにも迅速に対応できます。
- 患者の持病やアレルギー
- 緊急連絡先
- 家族構成や親しい友人の連絡先
これらの情報は、病院側にとっても非常に役立つものであり、迅速な対応を促す要因となるでしょう。
精神的なサポート
危篤の状況は、精神的に非常に負担が大きいものです。家族や友人は互いに支え合い、感情を共有することで乗り越える助けになります。以下に、効果的なサポート方法をいくつか挙げます:
- 話をすること:互いに思いを語り合うことで、感情の整理ができることがあります。
- リラクゼーション法の実践:深呼吸やストレッチなど、リラックスする方法を取り入れることが助けとなるでしょう。
- 必要な時はサポートを求める:精神的に辛い時は、専門家の助けを求めることをためらわないでください。
危篤状態の患者に対しては、直接的な接し方にも気を配る必要があります。優しく語りかけることや、手を握ることで安心感を与えることができるでしょう。
危篤時の葬儀準備
危篤状態が続く中で、心の準備を少しずつ進めることも重要です。残念ながら、亡くなることが避けられない場合、葬儀に関する基本的な理解を持っておくと、後の手続きがスムーズになります。
葬儀社との連絡
危篤の状態を見守りながら、葬儀社と連絡を取ることを考えてみましょう。葬儀社には多くの情報と経験があり、必要な手続きを整えるサポートをしてくれます。以下は葬儀社に連絡する際のポイントです:
- 相談の内容を明確にする:墓地や葬祭の希望を伝える。
- 日程や予算を考慮する:計画を進めやすくするため、希望の日時や予算に関する情報を準備します。
- 必要な書類について確認する:死亡診断書などの書類が必要となる場合が多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。
事前準備の重要性
万が一の際に、必要な手続きを混乱なく進めるために、事前に準備を整えておくことが大変重要です。具体的には、以下のようなことを心がけましょう:
- 照明の準備:当日は親族や友人等が集まり、明かりを灯し、神聖な空気を保ちます。
- 料理や飲み物の手配:集まる人たちのために、軽食を用意しておくと良いでしょう。
- 葬儀に関する情報の整理:希望するスタイルやテーマに基づいたプランを考えておくとスムーズです。
このように、危篤状態や、その後の葬儀手続きについて整理しておくことで、精神的な負担を軽減することができます。適切な情報を持ち、周囲とコミュニケーションを取りつつ、必要な対応を進めていくことが大切です。